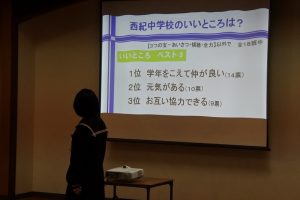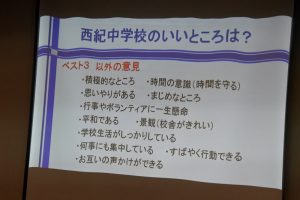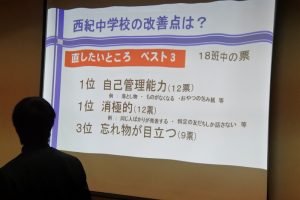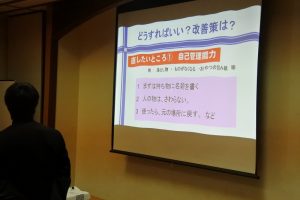3月3日(水)ABCマラソンが開催され、本校から計62名の生徒がボランティア活動を行いました。お城の三の丸広場には20名が参加し、スタート地点の誘導やゴールした方へのチップはずし、飲料水配布、メダルかけを行いました。また、本校前では給水所を生徒会が設営し、30名の生徒が水の提供しながら応援しました。この水は生徒会財源で、紙コップも生徒が集めてきたものです。また、吹奏楽部12名もセレモニーの演奏に参加しています。参加者の方や会場スタッフの方から、本当に一生懸命働いてくれて感謝していますとの言葉をいただいています。優しく温かい気持ちをもった生徒たちを誇らしく思います。